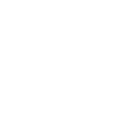第51回 2014年8月20日
[温故知新]カイガラムシの尻ぬぐい 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
庭や公園などで樹木の葉の表面や枝先にちょうど煤(すす)をまぶしたような黒いカビがはびこっているのを見かけたことはありませんか? ひどい時は葉の全面が真っ黒になってしまうので煤病(すすびょう)と呼ばれています。この煤病菌は植物体に入らず、表面に広がっていくので、そっとはがすと薄い紙を剥ぎ取るようにして取り除くことが出来ます。人の手の加わった庭や公園等ではよく見かけますが、山の中のような自然林ではあまり見かけません。
このカビはリマキヌラ・ジャヴァニカと言います。植物に寄生しているわけではなく、カイガラムシの排せつ物と植物体の表面に染み出てくる微量の分泌液のある場所を好んで繁殖するのです。つまり生命のない物質を分解吸収している典型的な腐生菌です。
カイガラムシは体が蝋(ろう)状の物質で覆われたり、殻があったりするために農薬を散布しても体に付着せず、防除が難しい害虫です。
さてこの煤病菌、寄生しないからといって植物に害がないわけではありません。葉の表面が煤で覆われてしまうため、大切な光合成を行うことが出来ず、生育に大きな影響が出ます。さらに、煤病菌の小さい胞子は風に乗って飛び回り、少しでも栄養分があるとそこに落ちて広がっていくのです。
実はこのカイガラムシの排せつ物は糖分を多く含んでいて、食品にも使用されていました。旧約聖書の出エジプト記に出てくるマナと呼ばれる食品は、砂漠地帯で低木に寄生したカイガラムシの排せつ物(甘露)を急速に乾燥して霜状に堆積したものと言われています。甘露と言うくらいですからきっと甘いのでしょうが、とても食べる気にはなれませんね。
煤病菌だけでなく、人間までがカイガラムシの尻ぬぐいをしていたのですから本当に驚きです。
第52回 2014年9月17日
[温故知新]カビの力で害虫駆除 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
人は病原微生物に感染しても、幾重にも存在する免疫系が効果的に作用して元の健康体に戻ることができます。でも昆虫にはそのような免疫機構はありません。昆虫が天敵の微生物に感染、発病すると死につながります。
1986年(昭和61年)のことです。鹿児島県の馬毛島で大量のイナゴが発生し、農作物が食い荒らされる大きな被害が出ました。ところがこのイナゴ、2週間ほどで突然島から消えてしまったのです。「今度は日本本土に上陸か」と大騒ぎになりました。何が起きたのでしょうか?
実はイナゴが突然消えた原因はカビだったのです。このカビはエントモファンガという昆虫に取り付くカビで、この年たまたま雨がよく降り、いつもの年よりこのカビが大発生したのです。このカビが取り付くと、2週間ほどで昆虫の体内に菌糸がはびこり、最後には苦しみもだえながら草をよじ登り、その先端でカビだらけの体をさらして死んでしまいます。その死体からは無数の胞子が飛び散り、次々にイナゴに感染していったのです。
日本にとって本土上陸の間際に神風が吹いたようなものですね。イナゴは農作物を食い荒らし、人間にとっては天敵ですが、イナゴの天敵はカビだったのです。
このように天敵である微生物をもって害虫を駆除する方法は微生物殺虫剤と呼ばれ、農業分野で応用されてきています。ボーベリア・ブロングニアルティというカビはゴマダラカミキリやキボシカミキリに病気を起こし死滅させます。またモナクロスポリウム・フィマトバカムというカビはサツマイモネコブセンチュウに効く生物農薬として出回っています。
当社でもメタリジウムというカビを使った害虫アザミウマを駆除する微生物農薬の原体を製造しています。この春オランダの会社から日本発の微生物殺虫剤として売り出されました。
かつてイナゴは農作物を食い荒らす敵であると同時に、貴重な蛋白(たんぱく)源でもありました。よく炒(い)って佃煮などにして食べたものです。カリッとした小エビのような食感を懐かしく思い出される方も多いと思います。今では作る人もほとんどいなくなり、本当に珍味になってしまいました。
第53回 2014年10月22日
[温故知新]謎多いマツタケ菌の世界 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
マツタケは古くから秋の味覚として日本人に親しまれてきました。マツタケ菌の学名は「トリコロマ・マツタケ」と言い、松の根に寄生する寄生菌です。
マツタケは生きている松の根から有機物をもらい、同時に松の根が養分を吸収するのを助けています。ですからマツタケの菌糸だけを育てても立派なマツタケにはなりません。マツタケを得るためには二者の共生関係を人工的に作り出すことが必要で、それは大変困難なことです。
マツタケの収穫量は年々減少し、最近では庶民には手が出せないほどの高い値段がつけられ店頭に並べられています。マツタケが採れなくなった理由の一つに松林に放置される枯れ枝や落葉が挙げられます。
以前、枯れ枝は家庭の燃料として利用されていたため松林の中は常にきれいでした。ところが枯れ枝や落葉が多くなると湿度が高くなり、これらを分解する微生物が多くなります。微生物が多くなると、これを餌にする虫や小動物が集まってくるためマツタケ菌の菌糸まで食害され、結果としてマツタケが採れなくなったと言われています。
さてマツタケがよく採れる場所には共通の条件があります。火山灰土壌は中性から酸性の土壌が多く、弱アルカリを好むマツタケ菌は生息しません。松林の土壌に生息している微生物の種類も問題で、細菌が多い場所や、ムキタケやナメコ、ナラタケ、タモギタケのような人工栽培が可能なキノコが多く見つかる所ではマツタケ菌は生育できないのです。
次に重要なのは松の樹齢です。20年以下の松林ではほとんど採れません。一般には30年以降からで、60年を過ぎると減少すると言われています。こうしてみるとマツタケ菌と松の根の活力との間には深い関係があることがうかがえます。単なる寄生菌であれば、宿主植物があれば菌が寄生しますが、マツタケ菌が発芽して成長を開始するためには厳密な条件が必要なのです。
いずれにせよまだまだ未知の部分も多いマツタケ菌の世界です。どうやら簡単にはマツタケ長者にはなれそうにありません。
第54回 2014年11月19日
[温故知新]やすり作り 味噌がミソ 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
広島も酒どころで、呉市にも多くの酒造会社があります。先日、そこの老杜氏(とうじ)が味噌(みそ)にまつわる面白い話をしてくれました。
近所のやすり工場の前を通ると味噌の焼けるいい匂いが漂ってきて、聞くとやすりに味噌を塗ってあぶっていたというのです。工業製品のやすりと食品の味噌、この妙な取り合わせに私は首をかしげました。
呉市は軍港でした。やすりは造船に欠かせないものとして発展し、今も日本のやすり生産の95%のシェアを誇っています。
やすりの材料は日本刀と同じ砂鉄を原料とする玉鋼(たまはがね)です。玉鋼は非常に硬く、やすりの目を切ることができません。そこで硬度を高める前に研磨をし、タガネと呼ばれる刃物が取り付けられた機械で1本ずつ目を切っていきます。
次が注目の味噌付け工程です。やすりの目立ての後、焼き入れをする前に味噌をゴシゴシ塗るのです。味噌付けされたやすりを約800度でドロドロになっている鉛の中に入れます。やすりが十分熱せられたら冷水に入れ、硬度を高めます。いわゆる焼き入れです。
味噌を塗るのはやすりの目に鉛がつまらないようにするためで、これにより完全な焼き入れができます。しかも味噌に含まれる炭素がやすりに吸収され、より硬いやすりが出来上がるのです。
味噌の種類や調合次第でやすりの仕上がりが変わるため、やすりメーカーにとってはどの味噌を使うかは企業秘密です。味噌は古ければ古いほど良いという職人もいれば、新しい方が良いという職人もいます。米麹(こめこうじ)だ、いやいや麦麹だ、塩分はいくらで色はどうだと百家争鳴。企業秘密の味噌は会社ごとに壷(つぼ)に入れて大切に保管していたことから、やすり屋さんの社名は「壷玉」「壷若」などみんな壷がつくのです。面白いですね。
味噌漬けがっこ自慢のお母さんたちとは別に、やすり職人もまた味噌漬けには熟練の技を必要とするのです。こうした知恵は昔の人が現在に残してくれた大きな遺産といえるでしょう。
第55回 2014年12月17日
[温故知新]人類の飢餓を救うカビ 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
人や動物の病気の多くは細菌によって起こされ、カビによる病気はわずかです。ところが植物の病気を起こす病原菌のほとんどはカビです。
フザリウムは土壌病原菌の代表。作物の導管を伝わって、あっという間に蔓延(まんえん)し、トマトの萎ちょう病やナスの半枯病などの病気を起こします。かつてアカカビ病に汚染された麦が原因で多くの食中毒患者が発生し、ロシアでは死者も出ました。フザリウム菌の生産する毒素によるものです。
こう聞くとフザリウム菌はカビの中の悪玉に聞こえますが、フザリウムの中には病原性の無いものもあります。この病原性の無いフザリウムは、培養すると菌体内に良質の蛋白質(たんぱくしつ)を豊富に作れるため、栄養価の優れた飼料や食料生産に活用できる可能性を持っているのです。
驚くことに24時間の培養で、菌体500グラムが10トンに増殖します。体重500キロの牛が1日に500グラムしか増えないのに比べると猛烈な増加ぶりです。
1981年初め、英国でマイコプロティンすなわちカビ蛋白製造プロジェクトが立ち上がりました。カビ蛋白を食用にするという概念は、日本の麹(こうじ)菌に代表されるように東洋では目新しいことではありませんが、西洋では物好きと見られました。
しかし、フザリウムを培養して得られた菌体マイコプロティンは非動物性蛋白で、本物の鶏肉や牛肉と識別できないほど天然の肉に食感と香りが酷似しています。しかも栄養に富み低脂肪でコレステロールがない健康的な食べ物です。今では菜食主義者のミートパイとして人気で、スーパーの店頭に並んでいます。
世界人口は着実に増え続け、従来の農業を主体とした食料生産手段ではもはや追いつかないと言われています。このフザリウムが作る蛋白源が解決の鍵を握っているかもしれません。
第56回 2015年1月21日
[温故知新]幼児期の食育 味覚に影響 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
人は料理を食べて「おいしい」と感じる味覚をどうやって身に付けるのでしょうか。また「舌が肥えている」と言われる人は何か特別な機能が備わっているのでしょうか。
人はもともと、生存に必要なものと害のあるものを見極めるためのセンサーを味について持っています。甘味はエネルギー源として、旨味は蛋白(たんぱく)源として、塩味はミネラル、酸味は腐ったものとして、苦味は毒物として認識します。
ビールなどで感じる苦味は本来毒のシグナル、食欲の増す酸味は腐敗のシグナルです。ペットの犬や猫を見ていると良くわかります。決して苦いもの酸っぱいものを好んでは食べません。
しかし人は「おいしさ」を「まろやかさ」や「こく」「味の切れ」「ふくらみ」に加え、食べ物の持つ記憶が複合的に結びついた形で味を判断します。これが、舌が肥えている人とそうでない人との違いともいえます。こうした感じ方の違いはどのようにして形成されていくのでしょうか。鍵を握るのが幼児期の食体験です。
県南部の味噌(みそ)は三十麹(こうじ)味噌といい、大豆1に対して3倍量の米を麹に変えます。大豆1に米1以下が平均的量ですから、いかに麹使用歩合が高いかが分かります。
日本全国を見渡しても、これほどの麹を使う味噌はありません。ですから県南部、特に横手平鹿地域の味噌を食べると違和感を持つ人もいるでしょうが、子供の頃にこの味に慣れ親しんだ人は、その味に故郷を感じ忘れられない味となるのです。
言ってみれば幼児期の舌を人質にとられたようなものです。食育が大切だと言うのはそういうことです。幼児期の食感や刺激が脳に刻み込まれるのです。子供だからと手を抜いてはいけません。子供だからこそ、故郷に伝わる伝統の味、手作りの家庭の味をしっかりと食べさせたいものです。
第57回 2015年2月18日
[温故知新]数表す単位に感動 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
今日は微生物の「微(び)」という字にまつわる話です。微生物というのは読んで字のごとく、微小な生物のことです。特定の分類群をさす言葉ではなく、ただ微小であるという特徴だけが共通の生物群です。
実はこの「微」、ちゃんと数字で表すことのできる漢数字の単位の一つなのです。
子供の頃、算数の教科書で大きい数の単位を知って感動しました。億(10の8乗)、兆(10の12乗)、京(10の16乗)…不可思議(10の64乗)、最後の無量大数(10の68乗)は仏教に由来します。その辺に落ちている細かい砂の一粒の直径を1兆倍すると地球より大きくなるなど多くのたとえ話がありましたね。
一方、小さい方は分(10分の1)、厘(100分の1)、毛(1000分の1)あたりまでは野球のアベレージなどで使いますが、それ以下はあまり知られていません。もちろん大きい数と同様実用的ではないからでしょう。
さて「微」ですが、これは100万分の1の単位で、長さの場合は1ミリの1000分の1(ミクロン)と同じです。麹(こうじ)菌の胞子が5ミクロンくらいですから、5微となるわけです。非常に小さいと言う意味の「微」という字は、肉眼では見ることができない菌の世界を表す単位にも使われているのです。まさに的を射た単位です。
ところでカビは肉眼で見ることができるのに、なぜ微生物と呼ぶのでしょう。実は私たちが見ているのは1個1個のカビの細胞が集まったものなのです。カビの1細胞は数ミクロンしかありません。単細胞が群体を作っているのがカビなのです。
江戸時代の数学のベストセラー「塵却記(じんこうき)」(吉田光由)によると、小数点以下にゼロが20も続く単位は、きれいなものという意味の清浄です。普段の会話でも使う「清浄」とは、煩悩や愚行が無く、心身が清らかであることとあります。
つまり、まったく見えないほど小さいものしかない世界、これ以上きれいにはならない世界を表す言葉なのです。数を表す単位にこめられた先人の見識に深い感動を覚えます。
第58回 2015年3月18日
[温故知新]細菌利用した「藍染」 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
ジーンズの生地デニムを作るのに使われ、日本で「藍」と呼ばれるインディゴは今ではほとんど合成品ですが、元々は熱帯植物由来の天然染料でした。
布地を染めるためには水に溶かして繊維に染み込ませなければなりませんが、インディゴは水に溶けません。そのためヨーロッパでは化学反応を起こしてから水に溶かすという複雑な工程を経て染色が行われています。一方、日本では細菌を利用した発酵法という独自の方法で作られています。
まず藍と呼ばれるタデ科の植物の葉を細かく刻んで乾燥させ、山積みにします。そして数日おきに水をかけながらかき混ぜると発酵が始まり、約3か月かけて「すくも」と呼ばれる堆肥状の発酵生産物が出来上がります。すくもの出来は水のかけ方、かき混ぜ方、温度の管理で大きく違ってきます。このすくもが染料の出来を大きく左右するため、藍師と呼ばれる職人が付きっきりで世話をするのです。
その後、藍師は保温のために土に埋め込んだつぼの中にぬるま湯を注ぎ、すくもと細菌の栄養源となる清酒や水あめと消石灰を入れ、好アルカリ菌で発酵を進めます。するとすくもに含まれているインディゴが酵素反応で還元され、水に溶ける染色液が出来上がります。染色液の仕込みから発酵が完了して染色可能になるまでの期間は、夏場で1~2週間、冬場で3~4週間ほどかかります。
こうして出来上がった染色液はロイコインディゴと呼ばれる黄色い色をしています。この中に繊維を浸けて引き上げると、空気に触れたロイコインディゴが反応を起こし、ジーンズ独特の美しい青色に発色するのです。藍染の布は消臭効果、細菌の増殖を抑制する効果、虫除け効果などもある優れものです。
今となってはほとんどが合成色素で染色されていますが、藍染を伝統産業として保護している徳島県では、藍住町という町まであって、今でもその伝統を守り伝えています。
第59回 2015年4月15日
[温故知新]カビでスギ花粉退治 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
花粉症の人にとっては嫌な季節がやってきました。
スギは今から200万年前に出現し、古くから優良な木材資源として盛んに植林が進められてきました。しかし、近年では花粉症の発生源として恐れられているようです。この国民病とも言われる花粉症の対策として、無花粉スギの植林が進められていますが、成長には長い年月がかかります。どうにかして花粉の発生を抑えることができないか――。様々な研究が進められ、注目されているのがカビを使った抑制法です。
古くから生き続けているスギの大木も人間と同様に多くの病気に悩まされています。スギの病原菌の大部分はカビです。
黒点枝枯病はその名が示すように枝枯れを起こします。この病気の元となるカビは、感染すると病患部に小さな黒点を多数形成します。早春、地表で越冬した落下スギ枝葉上にカビの子宮にあたる「子のう盤」が形成されます。その中には子のう胞子と呼ばれる10マイクロ・メートルくらいの胞子がカビの赤ちゃんとして入っています。胞子は3月上旬から空気中に放出され、花粉飛散中にスギ雄花に付着して感染します。花粉症に悩まされている人には信じられないでしょうが、この病原菌はスギ花粉が大好物なのです。
スギはわずか数マイクロ・メートルの病原胞子によって激しい枝枯れを起こし、ひどいときは山全体が真っ赤になり、まるで山火事にでもなったような状態になります。この胞子をスギ花粉撃退に利用してシューッとひと吹きスプレーしたいところですが、スギにとって病原菌だけに生態系や安全性への配慮が必要になりますから実用化は難しいでしょう。
同じくスギ雄花を可変させるシドウイアと呼ばれるカビが福島県のスギから見つかりました。スギの木を枯らすことなく、雄花だけを変異させるカビです。このカビをスギに感染させて翌年の花粉発生を抑えるという新技術が森林総合研究所で開発され、大規模な実施効果試験が始まりました。
カビを使って花粉を退治するこの方法、スギ花粉症に苦しむ全国の人にとって期待は大きいですね。
第60回 2015年5月20日
[温故知新]ペニシリン秘話(上) 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
第二次世界大戦中、戦場で負傷した兵士を1発の注射でよみがえらせるため「魔法の弾丸」と呼ばれたのがペニシリンです。英国では戦意高揚のポスターにまでなりました。それまでは、かすり傷程度の負傷をした兵士が、傷口から入った細菌が原因で死んでいくことが度々ありましたが、ペニシリンの登場で、見事に回復して前線に復帰できるようになったからです。
以前このコラムでも紹介しましたが、世界最初の抗生物質「ペニシリン」は全くの偶然から発見されました。1928年、ロンドンの病院に勤務していたフレミングが散らかった実験室を片付けようとした時のことです。ガラス容器を観察すると、黄色ブドウ球菌が一面に生えた培地に、雑菌の青カビが入り込んでいるのに気づきました。そしてその青カビの周囲だけが透明で、細菌の生育が阻止されているのを見つけたのです。彼は青カビを液体で培養し、その培養液をろ過した液に抗菌物質が含まれていることを見出しました。そして、青カビの属名であるペニシリウムにちなんで「ペニシリン」と名付けたのです。
しかし彼の世紀の大発見はその後10年ほどはかえりみられませんでした。41年にオックスフォード大学のフロリーとチェインらが青カビから抗生物質を抽出して医薬にすることに成功し、43年にはアメリカで大量生産が開始されました。
ペニシリンの発見で人類の寿命は10年延びたと言われています。45年にフレミングはノーベル生理学・医学賞を受賞しました。
実はペニシリン発見のずっと以前から、「阿仁のマタギ」の間では、化膿(かのう)止めとして、ご飯に生えたカビを飯粒とともに練り上げて傷口に塗るという民間療法があったそうです。そのカビが青カビかどうかは分かりませんが、カビの持つ抗菌作用を巧みに使った伝承の技です。
微生物の存在すら知りえなかった昔からノーベル賞級の知恵を持ち合わせていたマタギは、まさに秋田の誇りといえるでしょう。