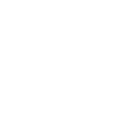第61回 2015年6月20日
[温故知新]ペニシリン秘話(下) 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
米国でペニシリンの大量生産が始まった頃、やっと日本にペニシリン情報がもたらされました。陸軍少佐の稲垣克彦医師が、ドイツ潜水艦Uボートで運ばれてきたドイツ医学誌からその論文を見つけ、碧素(へきそ)(ペニシリンの日本名)の研究が始まりました。
碧素の碧は青色のことで、青カビの色にちなんでいます。わずか6か月で「ペニシリンを完成させよ」という軍の命令があり、当時で15万円、現在の貨幣価値に換算すれば3億円相当の予算がつきました。1944年10月、ついに臨床試験に成功。国産ペニシリンの生産が開始されました。ちなみに3年後にはペニシリン協議会の登録会社は実に80社にも上りました。抗菌活性が低くても生産すれば売れる時代だったようです。
終戦を迎え、連合国軍総司令部(GHQ)はペニシリン研究の権威フォスター博士を米国から招き、日本人の指導にあたらせました。彼は、米国が6年の歳月と当時のお金で2000万ドルという莫大(ばくだい)な研究費を投じて得たペニシリン開発の秘訣(ひけつ)を、惜しげもなく全て公開しました。これにより彼は「日本のペニシリンの恩人」と言われています。
ペニシリンを作るための菌株、青カビQ176株も米国から与えられました。このQ176株は、かつて米国が優秀な菌株を必死に探していた時、農務省の北部農学研究所がある米イリノイ州・ペオリア市の一主婦が届けたメロンの青カビから分離したものです。この菌株は改良を続けながら、現在も使われています。
49年、日本ペニシリン協会創立3周年記念式典でGHQの当時のサムス大佐が次のように述べています。「現在、世界でペニシリンを自給できる国は三つしかありません。英国、米国、日本です」と。
敗戦直前の極限状態の中でペニシリンの研究を進め、戦後急速な発展を遂げたのは、米国や英国のペニシリン研究に負けまいとする多くの学者の努力のたまものでした。
さらに日本には古くから麹菌(こうじきん)を巧みに操る醸造という技術がありました。カビの種類は違っても、青カビを使ったペニシリン開発には日本の発酵というお家芸が生かされていたのです。
第62回 2015年7月18日
[温故知新]雷様の目覚まし効果 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
日本では古くから落雷でキノコが豊作になるという言い伝えがあります。現在、この伝承に科学的根拠を与える研究が進んでいます。私も実際、栽培されている場所に落雷があった後、一斉にシイタケが生えてきているのを見たことがあります。この現象は電気ショックが原因だということは容易に想像がつきます。また、落雷は雨を伴うことが多いので、ほだ木は水分を吸収でき、周辺にはオゾンが発生するなど総合的な影響でニョキニョキ生えてきたのではないかと考えられます。ただそのメカニズムは、まだ正確には、わかっていません。
シイタケの本体は菌糸です。これが枯れた木材を腐朽させ、菌糸体が蓄積されて「キノコのもと」を形成します。通常はこれに光、低温、水分、ガス環境などが影響して子実体(キノコの傘)になるわけです。キノコに限らず多くのカビは何らかの環境の激変によって身の危険を察し、自らの体(菌糸)を犠牲にして子孫を残すために生殖細胞(胞子)を作ります。
「俺はもうダメだ。でもいつの日か環境が良くなったら再生しよう。とりあえず子孫を残すために胞子を作ろう!」とするわけです。
実は種麹(たねこうじ)の製造でもその生物の本能(?)を利用した方法がとられています。胞子を作らせるために培養後半で乾燥させるのです。きっと麹菌は「こんな乾燥した中じゃ俺は生きられない。俺は死ぬが子孫に未来を託そう」とするからです。
体の免疫機能を高め、がん予防にも効果があるとされる成分を持つキノコの一種「鹿角霊芝(ろっかくれいし)」も、あの特徴的な鹿のような角を形成させるには煙ストレスが有効であるといわれています。
以前なかなか胞子を作らないカビに往生して、ほんの少し紫外線を照射したら、たちまち沢山の胞子を作りました。雷でキノコが目覚めるように、生き物にとってストレスは子孫を残すための手段のひとつなのです。
第63回 2015年8月22日
[温故知新]クモノスカビの隠し技 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
リゾープスというカビは生育が早く、一日で灰白色のくもの巣状に広がって見えるところからクモノスカビとも呼ばれています。リゾープスという学名はラテン語のリゾ(根)プス(脚)の合成語で、菌糸が伸びて、その名の通りカビには珍しい根(仮根)を持っています。
このカビを使って作られるのがテンペという食べ物です。インドネシアでは日本の豆腐のように日常的に食べられています。テンペは大豆を水煮し、皮を除いてからテンペ菌(リゾープス)で発酵させたものです。納豆のような糸引きや粘りはなく、白い菌糸に覆われたカマンベールチーズのような外観で、かすかに栗のような香りがします。これを切って揚げたり蒸したりして食べます。良質のたんぱく質やカルシウムに富み、繊維質や鉄分も多く含まれている高栄養の食品で、東京では給食に採り入れている学校もあります。
テンペの中に含まれている大豆の栄養成分は、テンペ菌の発酵によってパワーアップします。女性ホルモンに似た働きをする「イソフラボン」もテンペ菌の持つ酵素によってより人に吸収されやすい型になっているため、乳がんなどの女性疾患の予防や更年期障害の軽減、骨粗しょう症の予防に効果があるといわれています。第2次世界大戦の際、インドネシアのオランダ人捕虜収容所でテンペを食べさせることにより赤痢などの疾患に悩む捕虜たちの消化器官を守ったという有名な話があります。
リゾープスにはいくつかの種があり、果物、野菜類など多くの食品を変質させたり、サツマイモの軟腐病の原因となったりして厄介者扱いをされているものもあります。しかしリゾープスの中には胆汁酸を極めて効率よくステロイドホルモンのコルチゾンに変換できる菌がいるのです。まさに何の役にも立たないものから金を作り出す錬金術師のカビです。このカビの力に気づくまでは、32段階もの反応を経て化学合成され、ようやくコルチゾンに到達するという面倒なもので、しかも収量はわずか0・2%。とても高価なものでした。
これを聞いたらリゾープスはさぞかし人間の無能ぶりを笑うことでしょうね。
第64回 2015年9月19日
[温故知新]肥だめが支えた循環社会 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
先日気心の知れた仲間との飲み会で「肥だめ」の話になりました。肥だめは「ドツボ」とも呼ばれるそうです。ドツボにはまると抜け出せないし、臭いし、大変です。
今では見ることのなくなった「肥だめ」ですが、人ぷんは江戸時代には主要な肥料として活用されました。当時、江戸の街は世界一の人口を誇る100万人都市でした。そこで出る人ぷんは廃棄物ではなく、お金で買い取られる商品として流通していました。肥料の原料として再利用されていたのです。これを舟などで郊外まで運ぶ「おわい屋」と呼ばれる職業もありました。
面白いのはその人ぷんにもグレードがあったのです。武士の家から出る物は上物、商家は中物、町人長屋の物は下物として引き取られたのです。魚など動物性の食物を食べていた家のウンチは窒素分が豊富だったのでしょう。江戸の街から出る人ぷんはぜいたくな人々の排泄(はいせつ)物でしたから、農家も高値で引き取りました。天保年間にはこの人ぷんの争奪戦が勃発し、勘定奉行より公定価格が示されるほどの人気だったといいます。
私たちが子供の頃は、ここ秋田にも畑のいたる所に肥だめがありました。中にはふん尿が蓄えられ、畑にまくまでの間じっくりと「発酵」「熟成」されていました。
この過程が大変重要なのです。直射日光が当たらないように板で影を作り、その下にためます。発酵させるためには空気の入れ替えが重要で、そのため、柄の長い大きな黒いひしゃくで攪拌(かくはん)するのを見た方も多いと思います。肥だめはある意味衛生的な発酵装置ともいえます。
一定期間肥だめに入れることにより発酵が始まり、温度が上昇し、病気の原因となる病原菌や寄生虫を死滅させるのです。発酵という過程を踏まずにふん尿を直接肥料にすると大変なことになります。ふん尿の窒素は主にアンモニア態窒素で、土壌中にこれが多いと植物には有害です。また、ふんが分解する際のメタンガスや熱で作物にダメージを与えてしまうからです。
畑から肥だめがなくなってずいぶんたちます。化学肥料の普及や高度経済成長期の大量消費大量廃棄などにより、完璧に近かった我が国のふん尿のリサイクルシステムは完全に崩壊してしまったのです。
第65回 2015年10月17日
[温故知新]微生物に「ノーベル賞」を 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
今回ノーベル生理学・医学賞に輝いた大村智先生(北里大特別栄誉教授)の「この賞は微生物にあげたい」という言葉を聞き、微生物に対する認識を新たにされた方も多いと思います。
私もツエツエバエが媒介する熱帯病「眠り病」に効果を示す「放線菌」という微生物の大量培養を北里大から依頼され、お手伝いしたことがありましたので、今回の受賞を我が事のように喜びました。
1グラムの土壌には1億個の微生物がいるといわれ、その中から効率よく目的の菌を選び出すには工夫と経験が必要です。大村先生は地道な作業を経て、数千の菌から寄生虫の駆除薬として有望な数株を特定したのです。
特殊な能力を持つ菌はどこに隠れているか分かりませんから、私もチャック付きのポリ袋をいつも持ち歩いています。釣り人と同じで、どのような環境の所に隠れているか熟練してくると分かるのです。
この手の研究は宝探しのようなもので当たるかどうか分からないので論文になりにくく、若い研究者はやりたがりません。遺伝子解析などコンピューターを使って化合物を設計する研究が主流です。
しかし今回の受賞で、大村先生のような天然物(微生物)の中から有用なものを見つけ出す「微生物ハンター」方式の古めかしい手法がいかに大きな可能性を秘めているかを示してくれました。うれしいことです。
人類を救うような菌が見つかるのは単なる偶然ではありません。どんな場合も科学的基礎と観察力が備わってこそ発見があるのです。チャンスは誰にでもあるのですが、それは準備した人にしかめぐってこないのです。
どのような病気と闘う時も、そこには必ず私たちを助けてくれる微生物が存在します。私たちはこれまで地球上の微生物の多大な恩恵を得てきました。現在知られている菌類は約9万7千種。しかし推定総数は150万種ともいわれています。これらの未知の微生物は私たちの未来をこれからも確実に形作っていくことでしょう。
「微生物にお願いして裏切られたことがない」とは我が国応用微生物学の祖、坂口謹一郎先生の言葉です。まさにこの言葉を証明した今回のノーベル賞受賞です。
第66回 2015年11月21日
[温故知新]カビ 植物の香りで発芽 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
栄養の少ない土壌ではカビは生育できず休眠しています。ここに水と栄養が入ってきて地温が上がると、途端に目を覚まし発芽し増殖を始めます。
その引き金になるのが植物から出る香りです。香りを通じてカビと植物の間には密接な化学的対話がされているのです。例えば「ケトミウム」という木材を腐らせるカビは腐った木材からの香りの方向に発芽管を向けます。レモンの香り、リンゴの香り、干し草の香りで生育促進するカビも知られています。
森林火災の後、焼けた木の表面に鮮やかな桃色のカビがポッポッと生えてきます。これは繊維を好んで食べるカビで、「ノイロスポラ」と呼ばれます。木の焼けた臭いに発芽生育が促進されるのです。桃色をしたこの胞子はカロテン(ビタミンAの原料)です。
この胞子だけを集めて栄養剤を作ろうと試みた人もいましたが大量培養するのは容易なことではありませんでした。このカビには焼け跡の臭いが必要だったのです。
先日のこと、庭に落ちた柿があっという間に灰色のカビに覆われていました。これは「ムコール」というカビの仕業です。ムコールは熟した柿を見つけると目覚めて発芽し、付近を占領してしまいます。増殖が早く、競合する相手が発育する前に栄養を確保するのです。しかしまだこの香りの本体は解明されていません。
香りは水に溶けにくい性質があり、気体状態では迅速に遠方まで到達できますが、あまり長くは残りません。動物や植物、微生物が持っているフェロモンはギリシャ語のフェリン(運ぶ)とホルモン(興奮させる)を組み合わせた合成語で、体内で作り出した化学物質を体外に放出して同じ仲間に情報を伝達する物質です。
植物や微生物には鼻もないし、神経も脳もないのにちゃんと香り(フェロモン)を感じているのです。大昔原始人はフェロモンでコミュニケーションをしていたと考えられています。香りはいろいろな生物の生存を調節しているのです。
第67回 2015年12月19日
[温故知新]フグ毒 微生物が分解 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
先日金沢市の友人が当地の伝統的発酵食品である「フグ卵巣のぬか漬け」を持ってきてくれました。金沢近郊の美川(みかわ)地区で数軒が製造を許されている逸品です。「大丈夫だ。味見したけどこの通りピンピンしているぞ」と笑っています。
フグの卵巣は、それ1個で20人を死なせるほどの猛毒です。これを原料に使うだけでも信じられないのに、さらにその毒を発酵の力で無毒化しているのですから、まさに驚くべきことです。
フグは2月から6月の産卵期がおいしいと言われますが、この時期に毒性が強まるので始末が悪いのです。フグ毒(テトロドトキシン)は体内に入ってから早い時は20~30分、通常は3~6時間で発症します。まず舌や唇がしびれ、やがて知覚がまひし、呼吸困難に陥っていきます。恐ろしや、恐ろしや! 中毒のほとんどが素人のフグ料理で発生していますから、素人判断は禁物です。
これほどの猛毒を持っていながらフグ自身は何ともないから不思議です。フグの神経系はこの猛毒に感応しないのです。
実はこの毒はフグ自身の体内で作られるのではなく、摂取した海藻に付着している「シュワネラ・アルガ」という微生物や、そのほか複数のプランクトンや細菌類に由来します。これが「テトロドトキシン」を作るのです。結局フグは食物連鎖の過程で体内に猛毒をため込んでいたのです。
さて「フグ卵巣のぬか漬け」ですが、美川地区では明治初期より盛んに製造が行われ、マフグ、ゴマフグ、サバフグといった猛毒フグが原料です。その製造方法ですが、卵巣を30%という超高濃度の塩の中で1年間保存した後、ぬかに漬け込むそうです。
一般的な魚のぬか漬けに比べて塩の量が多く、発酵期間も長いのが特徴です。フグ卵巣の塩分より外の塩分濃度が高いため浸透圧が生じ、フグ卵巣の中の水分や毒素が外に移動します。そしてぬか漬けによって、残留した毒が耐塩性の乳酸菌や酵母を中心とした発酵微生物の作用を受けて分解され解毒されているのです。
「フグ卵巣のぬか漬け」の食中毒は皆無で、加賀の名物土産となっています。私もこの通りピンピンしています。
第68回 2016年1月23日
[温故知新]人工降雪で活躍する細菌 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
この冬は例年にない暖冬で、しばらくは雪かきや雪下ろしから解放され喜んだ方も多かったと思います。でも、雪国秋田は雪が降らないと困ってしまうこともたくさんあるようです。
冬の横手の伝統行事「かまくら」や湯沢の「犬っこまつり」など秋田の冬の祭りに雪は欠かせません。スキー場も雪を待ちわびています。ここ数日の大雪で、関係者の方たちもホッとしているのではないでしょうか。
この雪ですが、水の凍結する温度はその水の純度や周辺の環境、水滴の大きさによって異なります。水は0度で凍るものだと一般的に考えられていますが、不純物やゴミなどの混じっていないきれいな水は「振動を与えない」「ゆっくり温度を下げる」などの条件を満たすと「過冷却」という現象が発生して氷点下39度付近まで凍りません。
ところが「シュードモナス・フルオレセンス」という細菌を添加すると、それよりも高い温度で凍ってしまいます。
春の晩霜、秋の初霜は農作物に大きな被害を及ぼします。水滴は普通氷点下5度までは凍らないのになぜこの時期に農作物の葉の上についた水滴が凍るのか長い間不明でした。
トウモロコシ、クワ、茶の凍結による被害部位からその原因になっているいくつかの細菌が見つけ出され、霜害の発生には細菌が関与していることが分かりました。
このような細菌を「氷核細菌」と呼びます。この氷核細菌が分泌するタンパク質、糖、脂質などが混ざりあった物質が水の凍結温度を上昇させるのです。
空気中の水分は氷点下7度以下に冷却されると雪になります。ところがこの物質が存在すると、氷点下0・5度で雪になることがわかりました。
つまり、気温が0度を切るあたりで、殺菌して粉にした氷核細菌を混ぜた水をホースから霧のように噴き出せば、容易に雪を降らせることができるのです。この技術は人工降雪機に導入されていて、雪の少ないスキー場では必須のツールです。
この氷核細菌を使うことで0度に近い高温域での凍結が可能になるので、生鮮食品の風味や機能を保持する凍結促進剤など食品工業での活用が期待されています。微生物って我々人類がまだ知らない無限の可能性をたくさん持っているんですね。
第69回 2016年2月20日
[温故知新]大綱引き 支える微生物 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
私の生まれ育った刈和野(大仙市)には室町時代から伝わる自慢の大綱引きがあります。綱の直径約80センチ、長さは約200メートル、重さ約20トン。日本最大級の大綱は厳寒の2月10日の夜、古式にのっとり、町を上町と下町に二分し、観光客も含め、8000人近くで引き合われます。
私も毎年参加しています。勝負には負けたくないので「ジョウヤサノー」という掛け声に合わせ、精いっぱいの力を込めて大綱を引いています。今年は私も還暦を迎え、大綱の上から紅白の餅をまきました。とぐろを巻いた巨大な大綱の上に登ると身もすくむ思いでした。
その大綱は毎年新しい藁(わら)で1か月前から作られます。引き合い後、固く締まった結び目をほどき、全ての綱は浮嶋神社の境内に運ばれ奉納されます。そして1年をかけて、この20トンもの大綱は土に戻っていくのです。
子供の頃、初秋に神社に行くと、大綱がボロボロになり、肥えた土地にはミミズがたくさんいました。魚釣りの餌はここのミミズを使うのが常でした。
この大綱の分解を進めるのが微生物なのです。トリコデルマ・ビリディというカビは、シイタケのほだ木に付いてシイタケ菌を食べるので、シイタケ菌の有害菌です。
しかしこのカビは自然界では植物の細胞壁の成分であるセルロース(植物繊維)やカビ、キノコの細胞壁を分解してしまうので、自然界の掃除屋として人類にとっては有用な微生物です。
地球上の森林や河川が何万年も美しい姿を保っていられるのは、多くの微生物が植物や動物の遺体を最終的には水と炭酸ガスに分解してくれるからです。
もしも地球上にトリコデルマ菌が存在しなければ、地球は約10年で炭素循環が不可能になり、地球上の生物は絶滅すると言われています。刈和野の大綱が1年で跡形もなく消えて土になってしまうのも、このカビの仕業なのです。
500年の長い間、同じ場所で、目に見えない様々な微生物が、巨大な綱を分解し続けてきたのです。
以前その事実に注目した某大手食品会社が、この場所で食物繊維を分解する強力な分解酵素を見つけました。国の重要無形民俗文化財を陰で支え続けてきたこの場所は、まさに微生物が活躍する宝の山なのです。
第70回 2016年3月19日
[温故知新]雪解け促す木の体温 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
まだ残雪はありますが、北国の本格的な春ももうそこです。森の雪解けはいつも木の根元の幹から始まります。
これは幹の温かさによるものです。生きている樹木の中の水は外がどんなに寒くても凍ることはありません。夏だって外がどんなに暑くても煮えたぎることはなく、木立や森の中はひんやりとしていて、木の肌は冷たいですね。キノコを見つけて触れると、もっとしっとりして気味悪いほど冷たい。
枯れた木や伐採された木の肌は外気温と同じになり、キノコも乾くと冷たさは消えてしまいます。人や動物は死ぬと冷たくなりますが、樹勢のある木やキノコが死ぬと温かくなります。というより、どちらも温度調節機能がなくなり、外気温と同じになるというわけです。
樹木は根の先端から葉の先まで地下から上がってくる水に満たされています。井戸水が夏に冷たく、冬はお湯のように温かく感じるのは、地下水の温度が20度前後で安定しているからです。
この地下水が導管を通り、上に向かって動いてくるのです。春先に木々の幹と根元の雪が解けるのは、この温かさによるものです。雪解けのこの時期、庭の樹木に触れてみてください。木の温かさを感じ、木が生きていることを実感することでしょう。
水は植物にとって、光合成するために必要なだけでなく、細胞を満たしてなえないようにし、さらには体温調節までしているのです。
植物の維管束は動物の血管に、水は血液に相当する大切な働きをしています。土の中から根を通して吸い上げていた水が切れれば、木の体温が外気温と同じになってしまいます。植物に心臓はないのですが、水の流れが止まるのは心肺停止に等しいのです。
実は水を吸い上げるのは根だけではありません。菌根菌も一役担っています。菌根菌はほとんどの植物の根についています。これらは樹木が光合成で作った炭水化物をもらって生きています。代わりに土壌中から吸収した養分を樹木に渡します。
樹木は菌根菌がいないと養分をほとんど吸収できないため成長できないのです。樹木と菌根菌はまさに持ちつ持たれつの仲良しなのです。