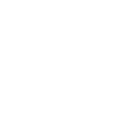第21回 2011年12月21日
[温故知新]香りの変化 麹造り左右 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
麹(こうじ)は発酵食品製造の要になるもので、その良否は最終製品の品質を左右すると言われています。造り手が一番神経を使うのが麹造りなのです。麹の出来に造り手は一喜一憂するわけです。醸造業は微生物との対話、感触を肌で感じ取る五感、いや六感をも駆使した経験が不可欠な産業です。
酒造りの杜氏(とうじ)さんたちは異常なまでに麹を造る時の香りの変化に気を使います。どうしてでしょうか。良い香りのする麹を使えば清酒の香りも良くなるといった意味も確かにあるでしょうが、主な目的は、麹の刻々と変化する香りを指標として麹の製造管理を行っているからなのです。
麹の香りの用語として知られているものに、オハグロ臭、栗香、キノコ香があります。名人杜氏は言います。「栗香が出たら麹を室から出せ。キノコ香がすると、出す時期を過ぎている」と。「1・オクテン・3・オール」というのがキノコ香の主体成分。麹菌の増殖が最も盛んな時期にはアルコールやケトン、アルデヒドのような青臭く感じられる成分が主体ですが、それ以後、これらの成分は減少してきて香りが質的に変化し、栗香が感じられ始めます。また、この時期から1・オクテン・3・オールが増加し続け、麹を出す時期になるとキノコ香が感じ取られるようになってくるのです。
麹培養の後半に出現するということは麹菌の老化と関係しているのかもしれません。この物質を感度良く捉えれば出麹の時期の判定に用いることができることを名人杜氏は知っていたのです。
1・オクテン・3・オールは別名「マツタケオール」と呼ばれるもので、日本人には好ましい香りですが、外国人には異臭に分類されます。「腐敗」と「発酵」の定義においても同様のことが言えますが、「好ましい香り」と「異臭」もまた、人間の価値基準により便宜的に決まるようです。
第22回 2012年1月25日
[温故知新]麹の悲鳴「オハグロ臭」 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
麹(こうじ)の香りを表す用語にオハグロ臭というのがあります。オハグロ臭とはいったいどんな臭いでしょうか。
オハグロは明治時代以前の日本や中国南東部、東南アジアの風習で、主に既婚女性の歯を黒く染める化粧法の一つです。オハグロは酢に鉄を溶かした悪臭の溶液に柿渋のタンニンを含む粉を混ぜることによって黒くなり、それを使っていたようです。主成分は酢酸第一鉄です。
名杜氏(とうじ)は言いました。「香りを嗅ぎながら麹を造れ!」「仲仕事前にはオハグロ臭がし、仲仕事後には消える」と。
仲仕事とは麹の増殖が最も盛んになる時期で、だいたい蒸米に種麹を散布してから32時間前後で行う作業。麹の温度は37~39度位になっている時期です。
この時期には麹菌の増殖が最も盛んになっていますが、自動麹製造機でもまだ麹は厚く盛り込まれていますので、酸素が不足になっています。酸素が不足するとアルデヒドと言われる香気成分(アセトアルデヒド、イソブチルアルデヒド、イソバレルアルデヒド)が顕著に増加していきます。この時期に杜氏がこの香りを感じ取り、麹に手を入れて酸素を供給してやるわけです。
擬人的な表現をすればオハグロ臭は麹の悲鳴です。「息苦しいから杜氏(とうじ)さん助けて! 空気を、酸素をください!」と言っているのかもしれません。杜氏がこの時期に手を入れてやらなければ麹は窒息してしまい、決して優良な麹が出来ないことを経験的に知っていたのです。
よく麹造りは口のきけない赤ちゃんに例えられます。寒かったら布団をかけてやり、暑かったら布団をはがしてやる。息苦しかったら新鮮な空気を――という具合です。
口がきけない麹菌と無言の対話ができる……。恐るべし杜氏の力!!
第23回 2012年3月14日
[温故知新]味噌が秘める予防効果 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
味噌(みそ)には様々な生理機能が知られており、昔から「寒にねぎ味噌を食べると風邪をひかない」とか「味噌はたばこの毒を抜く」といった言い伝えがあります。
一時は塩分の取り過ぎは高血圧の一因になるなどとして敬遠する人たちもいました。しかし、何事も過剰摂取をしなければ問題はなく、それ以上に味噌の持つ良い点が注目されるようになりました。
がんの予防、コレステロールの抑制・低下、老化の防止など味噌には秘めた様々な力があるのです。実はそのミラクルパワーのもとが麹(こうじ)菌なのです。
紫外線や活性酸素、たばこなどといった、正常な細胞に突然変異を引き起こす恐れがある変異原性物質は、人の細胞内の遺伝子に損傷を与え、がん細胞の異常な増殖を引き起こし、がん化を誘導する可能性があり、発がんに極めて密接な関係を持つと考えられてきました。
その作用を抑制する物質が、味噌からは複数発見されています。脂肪酸エステルや不飽和脂肪酸、イソフラボン類などがそれです。
中でも味噌の香りの主体である脂肪酸エステルは味噌の有用物質として最も早く報告された物質です。これらの生成には麹菌の作る酵素が密接に関与してきます。このような酵素が強ければ、変異細胞の暴走を抑える味噌の製造が可能になるのです。
私どもと県総合食品研究所は、味噌の持つこのような活性を従来よりも3倍も高めた、これまでにない高機能性味噌用麹菌「AOK139」の開発に成功しました。抗変異原性が直ちに抗腫瘍性となるものではないでしょうが、生体内で何らかの効果が期待されるものです。
この菌は第3回日本ものづくり大賞で、伝統技術の応用部門において生物系では初めて東北経済産業局長賞を受賞したほか、特許庁長官奨励賞も受賞しています。
第24回 2012年4月4日
[温故知新]カビから薬 免疫力調整 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
日本人の死亡原因の第1位はがんです。過去においてはがん治療の有効な手段は外科的治療、放射線化学療法が主体でしたが、近年、免疫治療が注目を浴びています。
免疫力を高めるものとして特に注目を集めているのが、カビの仲間のキノコに含まれるβ・D・グルカンです。β・D・グルカンは生体の免疫力の中でもとりわけT細胞の免疫力を高める作用があり、抗腫瘍効果をもつと言われています。
キノコから作られた抗がん剤が従来の抗がん剤と異なるのは、がん細胞を直接たたくのではなく、人が本来持っている免疫力を高めることによって間接的に、がん細胞に効果を発揮するという点です。
既に実用化され臨床の場で使われている抗がん剤にクレスチンという薬があります。これはサルノコシカケの一種です。またシイタケからはレンチナンという薬が作られています。これらの薬は国内で研究開発されたものです。
古来よりキノコの薬効に気付いていた日本人だからこそ作ることができた薬と言えるでしょう。
一方、カビで免疫力を抑える薬も作られています。臓器移植をする際、移植された臓器は体内でいわば異物として認識されるため拒絶反応を示します。異物を排除しようと免疫力が働くからです。
拒絶反応を抑え移植を成功させるためには、この免疫力をコントロールしなくてはなりません。そのため患者に免疫抑制剤が投与されるのです。
その中にカビから作られた薬があります。有名なシクロスポリンという薬です。この薬はノルウェーの土壌から分離されたトリポクラジウム・インフラタムというカビから作られます。
シクロスポリンが登場したおかげで臓器移植の成績は格段に向上しました。カビは免疫力を高めることも抑えることも出来るミラクルパワーを持っているのです。
第25回 2012年5月2日
[温故知新]麹のカビで絶品ハム 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
鰹(かつお)節に麹(こうじ)菌の仲間ユーロチウムというカビが必須であることは以前このコラムで紹介しました。実はヨーロッパと中国にもカビ付けして作る食べ物があるのです。スペインのハモンセラーノをご存じでしょうか。スペインの酒場「バル」に行くと、カウンターの上に必ずと言って良いほど載せられている熟成したハムです。
塩漬けした豚肉を長期間、気温の低い乾いた場所につるして乾燥させます。その際、この肉塊にユーロチウムが生育するのです。先日、東京・目黒のバルで秋田県産のハモンセラーノを食し、スペインの都市サラマンカで食した絶妙な味を思い出しました。鮮やかなピンク色とやわらかい食感、塩味も絶妙です。
さて、もうひとつの中国・浙江省金華名産の金華ハム「金華火腿(チンホアフトェイ)」にもユーロチウムは欠かせません。材料の金華豚は穀物などを一切与えず、茶殻や白菜などの発酵飼料で育てられます。そのため皮が薄く脂肪が少ないのが特徴です。
「火腿」も塩漬け後、風通しの良い場所で乾燥させます。本場中国では日本の鰹節と同様、スープの材料として使われています。カビって乾燥させたら生えないんじゃないの? と皆さん思われるかもしれませんが、実はユーロチウムというカビは普通のカビと異なり、乾燥した環境が大好きなのです。カビの酵素でグルタミン酸やイノシン酸が何倍にも増えて独特の旨味(うまみ)を作ります。
「キャビア、フォアグラ、トリュフ」は世界三大高級珍味と言われていますが、「鰹節、火腿、ハモンセラーノ」は麹カビが作る世界三大高級食材と言っても良いかもしれません。麹カビにも国境は無く、美味(おい)しいものを作るために魚や豚という素材の違いに関係なく遠い異国でも大活躍しています。さて今夜はどれを肴(さかな)に一杯やりましょうか。
第26回 2012年6月6日
[温故知新]カビは何でも食べる 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
カビはとてもしぶとくたくましい生物です。その食いっぷりたるや驚くばかりです。カビの大きな特徴は、生育していく時にあたかも人の汗のように体の外に有機物を分解する酵素をたくさん出し、それで分解されたものを栄養源として吸収することです。目的に応じて多種多様な酵素を分泌し、「まさかこんなものも?」と思う物まで食べてしまいます。
食品、衣類、家具などは言うに及ばず、アルミニウムまでも食べてしまうのです。航空機の燃料タンクの底やフィルターから「クラドスポリウム・レジネ」というカビが分離されます。このカビがせっせと食べ進めば燃料タンクに穴が開いてしまうかもしれません。ですから日本のように高温多湿な地域に売り込む航空機に使用されるアルミニウムは3層の樹脂コーティングがされているのです。
カビはこのほかにもプラスチック、塩ビ、カメラのレンズ、フロッピーディスクにまでとりつきます。しばらく使っていなかったフロッピーが機能しない時は、まずカビを疑ってもいいでしょう。
一般的にカビは弱酸性が好きなうえ、多糖類や脂肪酸が大好物で無添加化粧品などを放置しておけばカビだらけになります。人間の皮膚にとって栄養となるものはカビにとっても栄養なのです。
カビは食欲だけでなく適応力も抜群で、過酷な環境の中で突然変異しながら生き残っていきます。レンズに付くカビは乾燥した所にだけ生きる「ユーロチウム」という変わり者です。甘党(好糖性)もいれば辛党(好塩性)のカビもいます。また氷点下の低温でも生育するカビや硫酸の中でも生きられるカビまでいます。
偏食知らずで適応力あり……、これがカビの生き延びてきたコツです。
第27回 2012年7月11日
[温故知新]カビ、エコな農薬に変身 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
江戸時代の日本の文献に稲が無駄に伸びすぎて枯死する病気、稲馬鹿苗病が記載されています。その原因は稲に寄生したカビ「ジベリア・フジクロイ」が作るジベレリンという物質であることが後に明らかにされました。
実はこのジベレリン、種なしブドウを作る時に使われているのです。ブドウの花が開花する前後に花房をジベレリンの水溶液に浸(つ)けると、あら不思議、受粉しなくても種が出来ないまま立派なブドウになるのです。
このジベレリンはジベリア・フジクロイというカビを使って発酵生産されていて、農業で最も使われている植物ホルモンの一種です。他にもリンゴや梨の実を大きくしたり、ナスやイチゴの着果数を増加させるのにも使われます。このように成長促進、開花促進、果実の落下防止、老化阻止など幅広い目的に使われる優れものです。海外ではビール製造に必須である麦芽の酵素の誘導剤としても使われています。
さて先に紹介した稲馬鹿苗病ですが、箱育苗が普及するとともに馬鹿苗病防除のための稲の種子消毒は重要な作業の一つとなりました。種子消毒には合成農薬が多用され、その普及率は極めて高いものです。しかし、なにせ相手がカビですので病原菌の多くが農薬に対して抵抗性を示すようになり、また種子消毒廃液による環境汚染の問題も抱えています。
そこで出てきたのがカビをもってカビを制するという防除法です。自然に存在するものならば、人が合成して作り出した難分解物質(合成農薬)と異なり、安全であると考えられるからです。
実際ジベリア・フジクロイに強い拮抗能力を持つ「トリコデルマ」や「タラロマイセス」というカビが稲馬鹿苗病の防除カビとして現在広く使用されており、当社の主力製品の一つになっています。カビの特性を巧みに使った環境に優しい微生物農薬として注目されています。
第28回 2012年8月8日
[温故知新]死んだふりする水虫菌 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
しぶとい水虫に悩まされている方々も多いことでしょう。水虫患者は世界に5億人、10人に1人はいると言われています。かつて水虫はオヤジだけのもののように言われましたが、実はOLたちの中にも猛烈な足のかゆみに悩んでいる人が増えているそうです。
水虫を起こす犯人、それは「トリコフィトン」というカビです。このカビは人の皮膚の角質が大好きです。これまでもご紹介したように、ほとんどのカビは悪食で何でも食らいつきますが、このトリコフィトンは角質一筋です。
人の皮膚は表皮、真皮、皮下組織の三層で構成されますが一番上の層である表皮はさらに4つの層に分かれており、最外層にあるのがいわゆる角質層です。トリコフィトンは酵素を出しながら角質を溶かし菌糸を伸ばしていきます。
もともと角質の細胞は死んだ細胞、つまり垢(あか)ですので、異物の侵入に対する免疫反応が起きません。つまり痛くもかゆくもないから厄介なのです。しかし感染が進むと、やがて角質層下部の有棘層(ゆうしょくそう)の生きた細胞を刺激するので、痒(かゆ)くなり炎症反応が起きてくるのです。水虫の薬はトリコフィトンを殺す抗真菌剤の塗り薬が主力です。カビは真菌とも呼ばれ抗生物質は効きません。そこで真菌には真菌に効く抗真菌剤を使用することになるのです。
しかし、このカビ、抗真菌剤が来ると死んだふりをするのが得意なんです! 熊に出会ったら死んだふりをしろ!……あれです。
抗真菌剤が塗られ危険を察知すると自らの菌糸を太くしてその中に短い仕切りを作って休眠してしまいます。仕切られたひとつひとつの節は、やがて肥大し球状の耐久細胞を作ります。耐久というくらいですから多少の過酷な環境下であってもじっと我慢して生き延びます。なんとか生き延び、環境がよくなると再び発芽して菌糸を伸ばし角質を食べ続けるのです。このため水虫は治りにくいのです。
第29回 2012年9月5日
[温故知新]秋田弁 「腐る」使い分け 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
先日、県内の酒造関係者の集まりでのこと。「腐敗」を表す秋田弁の豊富なことが話題になり、大いに盛り上がりました。
まず「かぷける」。これは食べ物にカビが生えること。「あめる」は食べ物が腐ること。言わずと知れた代表的な秋田弁ですが、この現象を微生物学的に検証してみましょう。
「かぷける」は、同じ腐った様相でも、生える物自体の水分が少ないパンやお菓子のような固形物にカビが生えた様子を示し、臭いに重きを置いた表現ではありません。原因微生物がカビに限定されています。同じカビでも蒸米に麹(こうじ)菌を繁殖させた麹では、決して「ご飯がかぷけた」とは言いません。それは麹が人にとって有用だからです。
「あめる」は水分の多い物に生えてドロドロになった様を示します。あるいはその前兆を指して言うこともあります。ここに関与する微生物は細菌で、納豆菌のような原核生物の一種です。臭いに特徴があって、いわゆる「あめくせ臭い」がします。使い方としては「うわ!このご飯あめでらで!」などと使います。秋田の人は腐敗一つとっても、その原因微生物を見事に識別し、方言として生かしているのです。
「あめる」寸前には「すえた」臭い、酸っぱい臭いがしてきます。この原因菌は乳酸菌などの酸を作る細菌が関与しています。
さて、ご飯が「あめた」時の対処法ですが、昔は「水にうるがして、よぐ洗ってからお茶漬けにしてけ(たべなさい)!」と言ったものです。幸いなことに、あめる原因菌は納豆菌や乳酸菌の類ですから、食べられないわけではありません。しかもカビと異なり糸状に増殖しないので、容易に洗い流せるわけです。米の1粒まで大事にした東北人の心情が表れていますね。
第30回 2012年10月3日
[温故知新]麹づくり支えた天然杉 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
繊細な味と香りが求められる吟醸酒や大吟醸の品質を大きく左右するのが麹(こうじ)です。この「麹づくり」は高度な技術を有する杜氏(とうじ)でさえ安定的に造ることは難しいものです。名杜氏は、必ずと言っていいほど麹づくりに麹蓋と呼ばれる道具を使います。麹蓋は縦45センチ、横30センチ、深さ5センチほどの木製の麹を育てる器で、杉の正目で作られています。
ここに、だいたい1升の米麹が入ります。ヒノキやヒバだと抗菌作用が強く麹菌が育ちにくいため、麹蓋には昔から杉材が使われてきました。特に天然秋田杉の木目は年輪が1ミリと細かくそろっているのが特徴で、赤みを帯びた木肌は軟らかく加工しやすいため、割木職人に好まれます。底板は縞々(しましま)でザラザラしています。
麹蓋は天然杉を割って作るので、自然のデコボコで目と目の間に微小な溝が形成されます。このデコボコのおかげで通気性が良くなり、麹菌が活発に活動し、米に麹の花を咲かせることができるのです。麹は「糀」とも書きます。まさにこの状態を文字にしたものだったのです。
杉は、伐採されても死んでしまうわけではありません。木は呼吸し外気と麹蓋内部との水分の調整もしてくれますから、生きていると言えます。
菌糸は水分が多い方向へ伸びる性質があるため、麹表面よりも内部に向かって伸長し、結果的に優良な麹の代名詞である「ツキハゼ麹」が出来るのです。出来たばかりの麹は、まるで焼き栗のような香りがします。麹蓋は天然秋田杉の特性を知り尽くした割木職人によって作り出された天下の逸品なのです。
秋田は麹を使った発酵の国です。それを支えた麹蓋こそ「陰の立役者」と言えます。しかし東北森林管理局の決定により、2012年末で天然秋田杉の供給が終了します。来年から人工林杉の供給に変わるのです。銘醸家がこぞって求めた、あの赤みを帯びた微妙な風合いの麹蓋が消えてしまうことは、発酵の国・秋田の技の消失につながるのではないかと心配です。