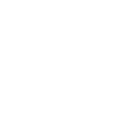第71回 2016年4月16日
[温故知新]聖なるキノコ 正体に注目 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
世界には宗教儀式に用いられる「聖なるキノコ」が3種類あります。ベニテングダケ、マンネンタケ、シビレタケです。いずれも県内で見かけるキノコです。
古代インドの聖典「リグ・ヴェーダ」の中に、飲んだ人に霊感を与え、恍惚(こうこつ)に満ちた讃歌(さんか)を歌い出せると書かれている「ソーマ」。その正体は長らく謎とされてきましたが、ソーマはベニテングダケであるという発表が注目を集めています。
ベニテングダケは童話の挿絵などに登場する最も親しまれているキノコですが、神経系に作用する毒キノコとして古くから知られています。このキノコには特徴的な二つの成分が含まれています。その一つ、「ムッシモール」は中枢神経に作用し、食べてから30分ほどで酒に酔った状態になります。よだれが出て、精神錯乱、幻覚を起こすこともありますが、死に至ることはないようです。
もう一つの成分の「イボテン酸」は調味料のグルタミン酸やイノシン酸の数十倍もの旨(うま)みを持っています。長野県ではこれを乾燥や塩蔵して食用にしている地域もあります。ただ摂取量など注意が必要なため、食用に推奨されるものではありません。
このベニテングダケこそがソーマであると発表した米国のゴードン・ワッソン氏は、かの有名なモルガン銀行の副頭取まで務めた金融マンでした。彼はメキシコやグアテマラでキノコを食べて幻覚状態を経験しました。
1955年にメキシコ南部の小さな村を訪れた彼は、実際に「幻を呼ぶ神のキノコ」を食べたのです。キノコによって夢幻の世界に陶酔する宗教的ともいえる習わしを、現地の人に交じって体験した冒険的報告は「魔法のキノコを訪ねて」という表題でライフ誌に掲載され、大きな反響を呼びました。
その後、儀式に用いられていたキノコはベニテングダケではなく、やはり幻覚を起こす物質が含まれているシビレタケであることが判明しました。スイスなどでは精神病の治療薬として一時使用されたこともあります。音楽家や画家などの中にも創作の際にこのキノコを利用する人が現れました。
幻覚を引き起こす物質は使い方によっては宗教の悟りに近い境地をもたらしますが、場合によっては狂気を引き起こす危険な物質でもあります。大脳の中枢に作用するこれらの物質が21世紀の医学界でどのような成長を遂げるのか楽しみであるとともに、気がかりでもあります。
第72回 2016年5月21日
[温故知新]秋田のうま味 しょっつる(上) 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
「水産物の発酵食品は?」と聞かれて、まず誰もが思い浮かべるのが塩辛でしょう。匂いや見かけからなんとなく微生物が働いていそうなので発酵食品と思っている方も多いかもしれません。
しかし、清酒や味噌(みそ)、ヨーグルトなどと違い、塩辛は発酵工程に種菌である酵母や麹(こうじ)菌、乳酸菌などの微生物は一切使われません。魚介類の筋肉、内臓に十数%の食塩を加えて腐敗を防ぎながら、その内臓に含まれる酵素の働きで自らの体を分解(消化)して、特有の風味を醸成させたものです。ここに微生物は一切絡んできませんから発酵食品とは言いがたいですね。
実は塩辛としょっつるは、魚介類と食塩のみを主原料として作られる点は共通しています。原料の魚介類に塩を加えて分解するまで熟成させ、液体部分を用いたのがしょっつるで、イカの形を残したいわば固形部分を食用としたものがイカの塩辛です。しょっつるの語源は塩汁がなまったものと言われています。
しょっつるは江戸時代から昭和初期までは食生活に欠かせないものでした。しかし醤油(しょうゆ)の普及により製造場は次々と廃業し、今ではわずかに残るだけとなってしまいました。
先日、男鹿のしょっつるメーカー「諸井醸造」におじゃましました。諸井さんのしょっつるの特徴は「ハタハタを使うこと」。えっ? しょっつるってハタハタが原料じゃないの? と思ったのは私だけではないはず!
実は使う魚はハタハタでなくてもいいのです。アジ、コサバ、イカ、ニシンなど様々な魚種が用いられるようです。諸井さんもいくつかの魚種でしょっつるを作っていましたが、彼はやはり「ハタハタ」にこだわりました。
いくら高価な魚になったとはいえ、ハタハタは秋田の魚。秋田音頭でうたわれている通り、「秋田名物八森ハタハタ~」ですからね。しょっつるにまつわる話の続きはまた次回に。
第73回 2016年6月18日
[温故知新]秋田のうま味 しょっつる(下) 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
前回に続き、しょっつるの話。男鹿のしょっつるメーカー「諸井醸造」のしょっつるは、水を一滴も加えずハタハタのみで高濃度の食塩とともに2年以上熟成させて製造されます。1トンのハタハタから500リットルのしょっつるができるそうです。魚体は70%以上水分ですから、しょっつるの水分は全てハタハタの体液由来なのです。
製造原理は醤油(しょうゆ)と同じで、たんぱく質を分解してできるアミノ酸でできています。ただし醤油は仕込む時に塩水を加え大豆のたんぱく質を麹(こうじ)の酵素で分解するのに対し、しょっつるはハタハタのたんぱく質をハタハタ自身の筋肉や肝臓の細胞に含まれる酵素で分解します。
塩は加えるものの、水は一切加えません。3年もたつと魚体は自己消化により完全に液化しトロトロになり、桶(おけ)の底には白い頭部と背骨とブリコだけが残り、表面にはペースト状の脂が浮いています。
しょっつるの製造工程ではこの脂を取り除くことが大事です。脂は不飽和脂肪酸を多く含むため酸化が進み、しょっつるの香りを悪くしてしまうからです。
真ん中の澄んだ液体だけを抜き取り煮沸し、濾過(ろか)した後に瓶詰め殺菌します。こうしたいくつもの過程を経て、あの澄んだ琥珀(こはく)色のしょっつるが出来上がるのです。
最近ではしょっつるの製造期間を短縮するために麹を添加したり酵素剤を添加したりする方法もあるようです。しょっつるの食塩濃度は25%前後で、醤油の17~18%よりははるかに高いのですが、味はしょっつるの方が濃く、塩分の割にはよく塩なれしていて塩辛さを感じさせません。
刺し身で食中毒を起こしやすい腸炎ビブリオは好塩菌といって2~3%程度の食塩があると増殖しますが、10%以上では増殖できません。その他腐敗細菌もこのような高濃度の塩分ではほとんど増殖できないので安心です。
さて今夜は諸井さんのしょっつるの隠し味で、海鮮焼きそばを肴(さかな)に一杯やりましょうか。
第74回 2016年7月23日
[温故知新]塩ウニ 熟成いらずの旨味 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
塩辛としょっつるは麹(こうじ)を使わず魚介類の自己消化酵素で分解することを先月紹介しましたが、読者から「塩ウニはどうだ?」と聞かれました。「塩ウニ」「からすみ」「このわた」は江戸時代から伝わる日本三大珍味で、なかなか手に入らない贅沢(ぜいたく)な一品として愛されてきました。
私たちが食べているのはウニの卵巣と精巣ですが、イカやしょっつると同様に内臓に含まれる酵素で自らの体を分解する自己消化が速いので、しばらく置くと身崩れを起こしてドロドロになってしまいます。
卵巣や精巣は生物にとって重要な器官ですから生きている間は自己消化が起こらないのですが、死ぬと一気に自己消化が進んでしまいます。
そこで塩蔵すると余分な水分が抜けて1年以上日持ちし、塩馴(な)れしてソフトキャラメルに近い舌触りと濃厚な風味となり、生ウニとは異なる味になります。
ウニの味を作るアミノ酸はグリシン、アラニン、グルタミン酸、バリン、メチオニンの五つですが、これらのバランスが崩れて分解されていく中で独特の美味しさが新たに出来上がっていくのです。
ちなみにメチオニンは単独では苦味がありますが、これを欠くとウニ独特の味がなくなり、エビやカニの味に似てしまうというから不思議です。
土産店で見かける瓶詰のウニは粒ウニと練りウニがありますが、塩とアルコールを加えたものです。塩ウニはイカの塩辛やしょっつるのように熟成による味の変化を期待するより、むしろ成分の変化を極力抑えて新鮮なウニの状態を保つことが重要なようです。
ウニには原料の段階で十分な旨味が含まれていて、イカのように熟成中に旨味の増加に頼る必要がないためでしょう。それ故、塩ウニはイカの塩辛のような長期熟成の必要がありません。ウニの塩辛とは言わず、塩ウニと呼ばれるゆえんです。
塩ウニは日本酒の最高の肴ですが、塩分やコレステロールも多いので、食べ過ぎには注意しましょう。自戒をこめて…。
第75回 2016年8月20日
[温故知新]花火支えた微生物 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
大仙市大曲の全国花火競技大会がまもなく開催されます。晴れるといいですね。
さて花火に必須の火薬は中国人の発明と言われていますが、この火薬の主成分は硝石です。実はこれこそ微生物によって作られるものなのです。
土壌中には硝化菌がいて、この菌が動物のふん尿や植物から生じたアンモニアを空気中の酸素を使って硝酸に変え、カリと結合して硝石を作るのです。このため中世ヨーロッパでは家畜小屋のふん尿を爆薬の原料にするため政府が管理するほどでした。
日本ではチリ硝石が輸入される明治中期まで、黒色火薬の主成分である塩(煙)硝の製造方法は、富山県五箇山地方で門外不出の技として400年近く守られていました。なにしろ爆薬の原料になるので軍事機密扱いです。秘密を守るために山奥で作り続けていたのです。
この方法たるや驚くべきものです。家の囲炉裏の床下にすり鉢状の穴を掘り、そこにヒエ殻やヨモギの茎を敷きつめ、その上に肥沃土(ひよくど)と蚕のふんと鶏ふんを混ぜ合わせたものを敷きます。
これを交互に何層にも重ね、最後に一番上から人の小便を大量にかけ土をかぶせ5~6年かけて硝化菌によって発酵を促します。
囲炉裏のそばに発酵穴があるので雪深い地でも凍ることはありません。硝化菌は蚕のふんや鶏ふん、人尿に含まれる尿酸や尿素をアンモニアに分解し、さらに酸化が進みます。
こうした長い発酵期間を経た土を桶(おけ)に移してたっぷりの水をふりかけると、桶底の口から出てきた液には硝酸が含まれています。
その液を釜で煮詰めて木灰を混ぜ、さらに煮詰めていくことにより木灰に含まれるカリウムと先の硝酸が結合し乾燥して硝酸カリウム(硝石)が出来るのです。いやはや実に高度な化学ですね。
現在では火薬そのものが進化し硝石を原料としない火薬に需要が移ったため、発酵法は全く姿を消してしまいましたが、今こうして花火を楽しめるのも微生物のなせる技と思うと感慨もひとしおです。いにしえの日本人の知恵と花火に思いをはせながら過ぎ行く夏の一夜をお楽しみください。
第76回 2016年9月10日
[温故知新]ユダヤ人救った細菌 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
今年6月、イスラエル中部の都市ネタニヤに杉原千畝(ちうね)にちなんで「スギハラ通り」が誕生したとの報道がありました。杉原千畝は第2次世界大戦当時、ナチス・ドイツの迫害から逃れた数千人のユダヤ人にビザを発給した日本人外交官です。彼は「命のビザ」で多くのユダヤ人を救いましたが、今日はユダヤ人を救った細菌の話です。
当時ユダヤ人は重大な病気にかかっているという診断書がない限り、強制収容所行きを免れることはできませんでした。そこでポーランドの小さな村に住む2人の医師が人の腸内細菌を使ってナチスをだますことを思いついたのです。
普通私たちが細菌に感染すると、体はその細菌だけに反応し、他には反応しない抗体をつくります。しかし高熱や発疹を伴う細菌感染症のチフスの場合は「プロテウスOX19」という別の細菌に対する抗体も血液中に出現します。
これは珍しい例ですが、チフス菌とプロテウス菌が共通の抗原を持つからです。チフスの診断テストで血液試料とチフス菌を混ぜると血液が凝集しますが、同じくプロテウスOX19を混ぜても血液が凝集するので、「すわ! チフスか?」と疑われるというシナリオです。
2人の医師は村に住む健康なユダヤ人にプロテウス菌を注射すれば体内にチフス抗体が出来、チフス患者になりすましてナチスをだますことが出来ると考えたのです。
この作戦は大成功。村人の体内にチフス抗体は作ったものの、いたって健康。それもそのはず、プロテウス菌は人の腸内に常在する細菌の一つだからです。
これによりこの村からは誰一人アウシュビッツ強制収容所に送られなかったのです。ナチスは25年以上前に大流行したチフスに対して異常な恐れを抱いていました。そのためこの小さな村でチフスが蔓延(まんえん)していると信じたのです。
人間の機知とプロテウス菌という細菌のおかげで小さな村は救われました。目に見えない微生物は神業をもやってのける不思議な力を持っているのです。
第77回 2016年10月22日
[温故知新]稲こうじ 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
稲刈りも終わり、すっかり晩秋のたたずまいです。稲の生育は気候に大きく左右されますが、稲には「適期刈り」というのがあるそうです。出穂後45日たち、毎日の平均気温を足して1000度に達した時、そして稲穂の9割以上が黄金色になり、枝分かれした稲の5番目が黄色くなった時、それが稲刈りの適期だとおいしい米作りをしている友人が話していました。
収穫間近になると毎日稲の様子を見て刈り取り時期を見極めるのだそうです。愛情と手間のかかったお米はおいしいですね。
この友人から「稲(いな)こうじ」について聞かれました。「稲こうじ」とは稲こうじ病のことで、稲のもみに病粒である黒い塊を作ります。一般に低温、日照不足、多雨などの条件で多発するようです。
稲こうじ病の病粒は「黒穂病」と外見は似ていますが、黒穂病の原因菌がキノコの仲間であるのに対し、稲こうじ病は稲こうじ菌というカビに感染して発病します。稲こうじ菌は「菌核」と呼ばれる硬く黒い胞子の塊を作るので、発病後に薬剤を散布しても効果はありません。
稲こうじ菌は麦角(ばっかく)菌の仲間で、「ウスチロキシン」というカビ毒を作るため人体には有害です。その形状から悪魔の爪とも呼ばれています。
友人は、「稲こうじ」という名称から稲こうじが麹(こうじ)菌のルーツで、酒やみそ、しょうゆに使う麹菌の野生種と思っていたようです。確かに以前はそう考えられたこともありましたが、現在では遺伝子解析も進み稲こうじ菌と醸造用の麹菌は全く関係がないことが知られています。
「天然」「自然」という言葉を安全安心と安易に結びつける風潮がありますが、こと人の口に入るカビについては天然起源の場合は要注意です。カビの中にはカビ毒をつくる野生のカビがたくさん生息しているからです。
野外から醸造用の麹菌が採取されることはありません。では醸造用麹菌のルーツは……。次回のお楽しみにとっておくことにしましょう。
第78回 2016年11月19日
[温故知新]悪魔の双子 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
長い歴史の中で、人間は野生の動物を家畜化し利用してきました。イノシシから豚を、カモからアヒルをというように。植物も野生の稲や麦を栽培しやすいように品種改良をしてきました。微生物もまた同じです。
微生物には人間と同じように名字と名前があります。名字に当たる属名をラテン語で最初に表示し、その後に名前に相当する種名がきます。醸造に使われる麹(こうじ)菌の場合、名字(属名)はアスペルギルスで、名前(種名)がオリゼです。
さて、前回紹介したように野外から麹菌が採取されたことはありません。日本醸造学会では醸造に用いられる麹菌と野生の麹カビを明確に分けています。2005年に麹菌の遺伝子解析により、長い間謎であった麹菌のルーツが明らかになりました。
麹菌(アスペルギルス オリゼ)は野生のカビ毒を作る麹カビ(アスペルギルス フラブス)を祖先とし、醸造用麹菌に進化していったのです。それはたった1%の遺伝情報の違いによるものです。よって欧米の菌学者たちはこの二つの関係を「デビルツイン」すなわち「悪魔の双子」と呼びます。片方が天使で片方が悪魔の双子です。
このカビ毒を作る双子の片割れ野生の「フラブス」にも毒を作らなければならない事情があります。どんな生物でも身を守る必要に迫られる時があります。外敵に襲われた時、イノシシであれば牙を武器にして身を守ります。
フラブスにとってその牙がカビ毒だったのです。やがてイノシシが家畜化され人に守られるようになると牙は必要なくなり豚になりました。
同様にフラブスも長い歴史の中で「蒸米」というとても栄養豊かな環境下で生育することで外敵から身を守る必要がなくなり、毒を作り出す能力を完全に失い、無毒なオリゼに変化していったのだと考えられています。
2006年に日本醸造学会は「日の丸が国旗、君が代が国歌」のように日本の食文化を支えるカビ毒を全く作らない安全安心なミクロの巨人「麹菌」を「国菌」に認定しました。
第79回 2016年12月17日
[温故知新]どぶろく 発展の理由 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
「どぶろく」は「濁酒」とも呼ばれ、酒税法では清酒と区別して「米、米麹(こうじ)及び水を原料として発酵させたもので、濾(こ)さないもの」との規定があります。
「どぶろく」の起源は定かではありませんが、中国や朝鮮から稲作とともに伝わった、米で造る醪(もろみ)の混じった状態の濁酒を「濁醪(だくろう)」と呼んだのがなまって今日の「どぶろく」になったといわれています。
清酒は酒税法上で「濾す」という工程が必要ですので、清酒メーカーの販売している「濁り酒」は清酒の醪を「濾す」という作業が必ず入っています。「濾す」から澄んだ酒で「清酒」なのです。どぶろくは米を使った酒類の最も素朴な形態といえます。
濾すことをしないので、未発酵の米粒や米麹、酵母が入っていますから飲むというより食べるといった感じがします。どぶろくを飲むとおなかいっぱいになるのはこのためです。
日本海に面し5か月近くも雪に埋もれている秋田の農民にとって、酒は嗜好(しこう)飲料というよりも日常生活の必需飲料であったようです。非合法と知りつつ、多額の罰金を科されることにおののきながらも、隠す戦術に腐心し、地下へ天井裏へと収税官(酒調べ)との知恵比べを展開していました。
秋田県はかつて「どぶろく密造日本一」と言われていました。摘発件数が最も多かったのは1961~63年で、1年間に3500件以上にも上りました。この頃は豊作続きで、どぶろくも隆盛を極めたようです。秋田は古くから雑穀に対しての米食比率が全国一高く、冷害の続いた年にも秋田(羽後の国)の領民は1人平均1斗(15キロ・グラム)の米を麹に変えたといいます。
豊富な米は多様な米食とともにどぶろくも発展させました。秋田の先人たちは飽きることなく飲んではおいしく、食してはうまい高度な味を麹に求めた歴史があるのです。
不名誉な「どぶろく王国」の名ですが、秋田県の検挙者数が多かったのは、他県に比べて密造取り締まりに対して厳しかった、つまり忠実かつ熱心な収税官が多かったためと思われます。
この時期「どぶろく名人」から作品をいただきますが、どれもこれも逸品ばかりで思わずうなってしまいます。
第80回 2017年1月21日
[温故知新]幻の鰰エラ寿司 今野宏(寄稿)
◇秋田今野商店社長
県内各地に「ナッツ」と呼ばれる「飯(いい)ずし」の原型と思われる発酵食品があります。
ナッツは木の実のことではありません。
飯ずしと塩辛の中間のようなもので、かつては長期間貯蔵できる食べ物として重宝されたようです。大きな特徴は飯や麹(こうじ)を使わず、塩だけで自然発酵させている点です。魚体の持つ酵素で自分自身を分解する自己消化による発酵食品のひとつです。
魚の身には雑菌が少ないのですが、内臓やエラ、皮などには雑菌が潜んでいます。ですからエラもエラの裏側の肉も一般的には生で食べることはありません。
しかし加熱調理したものは、鰰(はたはた)に限らず魚のエラの裏側の肉は白身と違い、肉質が締まっていて弾力があり、旨味が凝縮されています。
鰰の一匹寿司(ずし)の場合、オスはエラの部分から、ブリコの入ったメスは頭だけを切り落とし、内臓を取り除いてから漬けるのが一般的です。エラから上の頭を食べることはまずありえないものだと思っていました。
ところが昭和30年代、大館市の猿間地区には「ササメナッツ」という鰰のエラの裏側の肉とブリコに麹と菊の花、からし菜、塩を加えて刻み、よく混ぜて漬けた変形鰰寿司があったことを知りました。ナッツといってもこれは麹が使われていたようです。
そんな幻の鰰寿司にお目にかかることはもうできないだろうと諦めていたら、在京の元雑誌編集者の八代有子さんから「能代に住む弟が幻の鰰寿司について書いたコラムがある」とその内容を送ってくれました。
それによると、「米と麹と薄切り人参(にんじん)にふのりに畳まれた頭とエラがあった。のど側からきれいに蝶(ちょう)のように切り広げられており、実に丁寧に下処理されたことが分かった。食べると骨と軟骨の硬さは気にならず、なんともいえぬ歯ごたえ。しっかりした重石(おもし)による漬かり具合のよさを感じた」とあります。
私は居ても立ってもおられず、早速能代の八代保さんを訪ねました。やっと会えた幻の鰰エラ寿司。言うまでもなく酒が進み、楽しい一時でした。